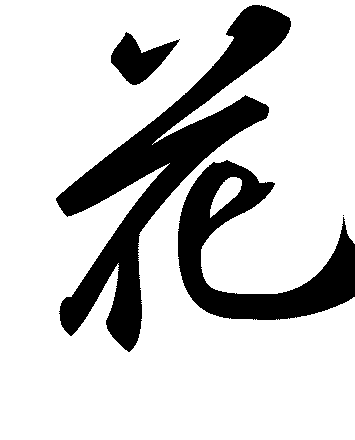
|
||||||||
|
|
||||||||
|
稲畑 汀子 |
|
|
|
俳句十二ヵ月
理事長 稲畑 汀子
春の足音 ― 二月 ―二月四日頃の立春を過ぎるともう春です。気温はまだ低く、なお冬を引きずってはいても、春という声を聞くだけで心が明るくなり期待に胸がふくらみます。
寒くとも「春寒」と言うことで心が弾み、同じ寒さでも「余寒」と言えばまだ冬の寒さが尾を引いている感じのほうに力点がかかります。雪解が始まり、氷がだんだん薄くなっていくにつれ「猫の恋」という季題に見られるように動物や植物の生の営みも活発になります。「白魚」「公魚」「えり挿す」などの季題は活動を始めた魚たちに対して人間が漁という形で対応して生きてきたことを示す良い例でしょう。野焼や山焼が始まるのもこの頃です。
一般の人も冬構えを解き、窓を開け、外に出ることが多くなります。
猫柳やクロッカス、片栗の花、雪割草、蕗の薹などが早春の光を返して光っているのを見つけるとき、誰もが生命の復活を感じ喜びに心が満たされます。そんな中でも昔から人々が得に喜び賞でてきたのは、何といっても「梅の花」ではないでしょうか。春の魁として開くその清楚で端正な花の姿形とともに馥郁とした香がこよなく愛され、梅の花は早春のシンボルとして多くの詩歌に詠まれてきました。おそらく日本人は梅の花を見ることによって春の足音を確かなものとして身内に感じてきたのだと思います。離れても充分に寒さというものを鋭く美しく表現し得ていると思います。
早春の光もろとも釣れしもの 山田弘子
釣り上げた瞬間、魚がきらっと光ったのですね。魚が光ったのではありますが、それは早春の光を返して光ったのです。作者はその情景を詠み止めて「早春の光と一緒に釣れた」と表現しています。まだ寒いけれど光が眩しい二月の季節感を見事に表現して素晴らしいと思います。
NHK出版 俳句十二ヵ月 より
本のご紹介
NHK出版 俳句十二ヵ月〜自然とともに生きる俳句〜
NHK俳壇の本
俳句十二ヵ月〜自然とともに生きる俳句〜
著者 稲畑汀子
発行 安藤龍男
発行所 日本放送出版協会
定価 本体1600円+税日本に暮らす。俳句と暮らす。
現代俳壇の祖・高浜虚子の孫であり、俳誌「ホトトギス」の現主宰である筆者が、俳句とともに季節を生きる喜びと、虚子直伝の俳句の骨法を、やさしく語る。
季節の言葉「季題」を、古今の名句・美しい写真・実作のエピソードをもとに紹介する第一章「季節を友として」、虚子名言集をもとにした実作解説の第二章「ホトトギスの教え」、自然とともに生きる俳句の豊かさを語る第三章「自然と人間」等、見て美しい、読んでためになる一冊。
俳句の世界に興味を持つ人から、句歴の深い人まで、俳句を愛するすべての人へ贈る、十二か月を俳句と暮らすための俳句入門書。